学習指導要領と令和の日本型学校教育,GIGAスクール構想
令和2年度から施行された現行の【学習指導要領】(平成29年告示),中教審答申の【令和の日本型学校教育】,前倒しで進められた【GIGAスクール構想】を簡単に紹介します。本校教育を理解する一助となれば幸いです。
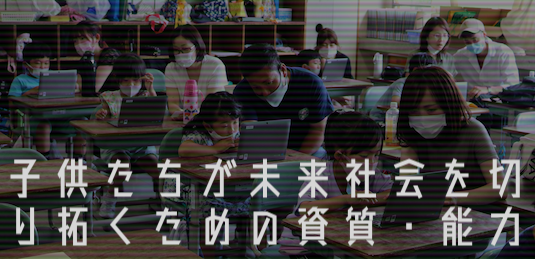
1 現行の学習指導要領
⑴基本的な考え方
㋐これまでの学校教育を生かし,子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力(生きる力)を確実に育成します。それを社会と共有し,連携するための「社会に開かれた教育課程」を実現します。
㋑知識及び技能の習得と,思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視し,知識の理解の質を更に高め,確かな学力を育成します。
㋒道徳教育の充実や体験活動の重視,体育・健康に関する指導の充実によって,豊かな心や健やかな体を育成します。
⑵育成を目指す資質・能力の明確化
「生きる力」に求められる資質・能力を,次の3つの柱に整理します。
㋐「何を理解しているか,何ができるか」(生きて働く「知識・技能」の習得)
㋑「理解していること・できることをどう使うか」(未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成)
㋒「どのように社会・世界と関わり,よりよい人生を送るか」(学びを人生や社会に活かそうとする「学びに向かう力・人間性」の涵養)
⑶「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進
子供たちが,⑴の3つの資質・能力を身に付けるには,授業の質向上が必要です。
子供が自ら取り組み,必要とするときに,互いに学び合い刺激を受け合いながら,学びを深化拡充する…,そのような授業(学習の在り方)を創り上げます。
⑷学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進
⑴⑵⑶を実現するために,各学校では,教育課程の基づき教育活動の質の向上を図るPDCAを行います(カリキュラム・マネジメント)。
各学年では,目標を実現するために,児童や学校・学級,地域の実態を考慮し,必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立て,学年経営の礎とします。
| 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 | アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善 |
|---|---|
| 学習の基盤となる資質・能力 | 言語能力,情報活用能力,問題発見・解決能力など |
| 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力 | 豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成すること |
| 教科等横断的な学習 | 児童や学校,地域の実態を適切に把握し,教育の目的や目標の実現に必要な各教科・領域の学習内容(コンテンツ)・育成する資質・能力(コンピテンシー)をねらいを持って組み合わせ関連づけた学習のまとまり。生活科(1・2年)や総合的な学習の時間(3〜6年)などに代表される。 |
2 令和の日本型学校教育
教審答申(令和3年1月)として打ち出された,「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~ は,現行の学習指導要領を補完・具体化した内容です。
その主旨は,次の2点です。
⑴義務教育において決して誰一人取り残さないことを徹底し,多様な子供一人一人が自立した学習者として学び続けていけるようにする。
⑵子供がICTも活用しながら自ら学習を調整しながら学んでいくことができるよう「個に応じた指導」を充実する。
「個に応じた指導」は,子供側からみれば「個別最適な学び」と称されます。さらに,「個別最適な学び」は,「指導の個別化」と「学習の個性化」によって実現されます。
| 「指導の個別化」 | 教師が,指導方法・教材・学習時間等を柔軟な設定にすることによって → 子供が,特性・学習進度・学習到達度等に応じた学習方法を選べること。 |
|---|---|
| 「学習の個性化」 | 教師が,個に応じた学習課題や学習内容を設定することで → 子供が,興味・関心,キャリア形成の方向性等に応じた学習内容を選べること。 また,「個別最適な学び」が孤立した学びにならないように「協働的な学び」を充実することも重要とされています。 |
| 「協働的な学び」 | 教師と子供,子供同士の関わり合い,自分の感覚や行為を通して理解する実習・実験,地域社会での体験活動など,様々な場面でリアルな体験を通じて学ぶこと。 |
3 GIGAスクール構想
前述した「主体的・対話的で深い学び」(「個別最適な学び」と「協働的な学び」)を実現するための基盤が,「GIGAスクール構想」による子供一人1台タブレット端末配備です。
「個別最適な学び」と「協働的な学び」を成立させるには,教師が子供の成長やつまずき,悩みなどの理解に努め,個々の興味・関心・意欲等を踏まえてきめ細かく指導・支援することと,子供が自らの学習の状況を把握し,主体的に学習を調整することができるようにすることが必要です。
ICT(タブレット端末)により,子供一人一人の学習履歴(スタディ・ログ)や生徒指導上のデータ,健康診断情報等を利活用する必要があるのです。
そのため,GIGAスクール構想により配備される1人1台の端末は,クラウドの活用を前提とし,高速大容量ネットワークを整備し,教育情報セキュリティポリシー等でクラウドの活用を禁止せず,必要なセキュリティ対策を講じた上で活用することとなっています。
| 「クラウド バイ デフォルト」 | 子供や教職員が生み出したデータ等を端末には保存せず,インターネットで結んだ他所へ保存する環境。山形市の場合は,市教委指定の業者サーバへ自動的に保存される仕組みとなっている。そのため,子供たちがタブレット端末を家庭へ持ち帰り学習を継続すること等も可能になります。 |
|---|
